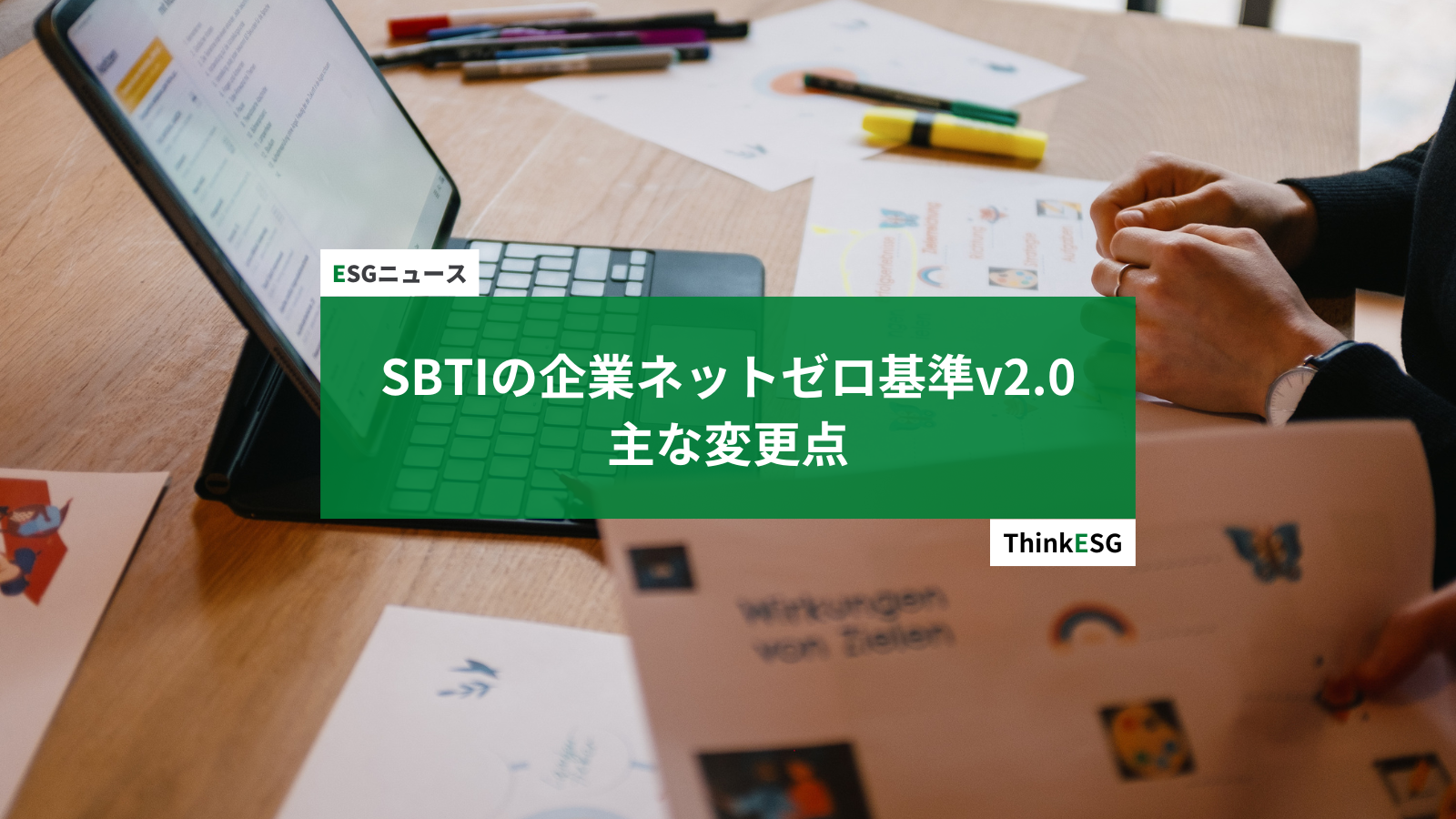企業の温室効果ガス排出量削減目標設定の主要基準策定機関であるSBTIは、企業向けネットゼロ基準バージョン2.0の最終草案を公表した。同草案はネットゼロ目標達成に向けた企業行動の柔軟性を強化すると同時に、実質ゼロ達成までの過程で削減しきれない継続的な排出量への責任ある対応を義務化する方向へ移行している。
主なポイント
• 主な更新点:スコープ3目標達成方法の明確化、義務的な移行計画への対応を評価
• 今回の改訂案への意見提出期限は12月8日
• 現行スケジュールでは、新基準は来年(2026年)公表され、2028年に義務化される見込み
サイエンス・ベースド・ターゲッツ・イニシアチブ(SBTi)は、気候変動対策へ資金提供や炭素除去投資を評価し、企業のスコープ2(購入した電力などの間接的な排出量)及びスコープ3(原材料の調達から廃棄までのサプライチェーン全体で生じる他社の活動に伴う排出量)の削減コミットメントに関する明確な指針を提供し、移行計画に含めるべき内容を規定する、次期「企業ネットゼロ基準」の97ページに及ぶ草案を公開した。2025年3月にリリースされた同基準の初期ドラフトから大幅な更新となる。
基準バージョン2.0へのこれらの改訂は、3月中旬に公開された前回草案に対する850以上のステークホルダーからのフィードバックに基づく。SBTIは12月8日までに再度の意見募集を実施する。
アルベルト・カリロ・ピネダSBTi最高技術責任者(CTO)は声明で「本草案へのさらなる意見は、最終版『企業ネットゼロ基準』の実用性・信頼性・堅牢性を確保し、世界中の企業がネットゼロ移行を加速する上で極めて重要だ」と述べた。
約12,000社がSBTiのルールを用いて温室効果ガス削減目標を設定しており、約2,200社が2050年またはそれ以前にネットゼロを達成する公約を検証済み、2,800社が目標設定プロセス中である。
11月3日に公表されたSBTi報告書によると、ネットゼロ目標を設定した企業の4分の3以上が、この公約が投資家の信頼向上に寄与したと回答している。しかし、ネットゼロ目標の見直しが進む中、一部の大手企業は他のアプローチを優先し、この枠組みから距離を置く動きを見せている。
継続的排出量への対応に関する新たな認定オプション
これまでSBTiは主に、企業の排出量削減目標設定に向けた指針提供に注力してきた。11月6日に公表された草案における最大の変更点の一つは、その適用範囲を拡大し、ネットゼロ移行期間中に排出される温室効果ガスに対する企業の責任の取り方に関する指示を含めることである。ガイドラインは当面任意適用となり、2035年に義務化される。
カーボンクレジットの活用は今後義務付けられるか?
SBTiが「継続的排出責任(OER)フレームワーク」を通じて企業のネットゼロ戦略におけるカーボンクレジットを体系的に認定する仕組みを構築したのは今回が初めてである。これは「バリューチェーンを超えた緩和(BVCM)」という用語に代わるものだ。カーボンクレジットが単なる任意の追加要素ではなく、ネットゼロ達成への道筋の一部となるという重大な転換を示している。*2
OERフレームワークとは?
OER(Ongoing Emissions Responsibility)フレームワークは、
ここから先は「ThinkESG プレミアム」会員限定の
コンテンツです。
4つの特典が受けられる「ThinkESG プレミアム会員(1ヶ月定期購読)」の詳細についてはこちらをご覧ください。
「ThinkESG プレミアム会員(1ヶ月定期購読)」へはこちらからお申し込みいただけます。