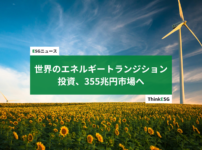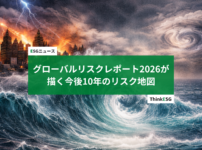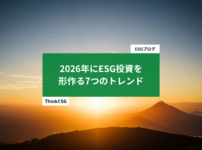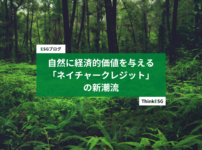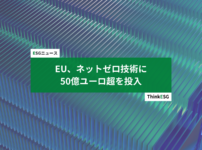ThinkESGプレミアム会員限定
冬季オリンピックは、雪と氷という自然条件を前提に成立してきた大会である。しかし近年、気温上昇や降雪量の減少により、その前提そのものが揺らいでいる。2026年2月6日〜2月22日に開幕中のミラノ・コルティナ大会では、競技用雪の大部分が人工的に補われている。人工雪は大会を支える一方で、安全性や資源負荷という新たな課題も浮き彫りにしている。本記事では、複数の報道や研究をもとに、冬季オリンピックが直面する現実を整理する。
冬季オリンピックは、制約の中で開幕した
2026年2月6日、イタリアでミラノ・コルティナ冬季オリンピックが開幕した。大会は2月22日までの17日間にわたって開催される。今回の冬季オリンピックは、過去の大会と比べても、より温暖化が進行した環境下で実施されている。米ABC Newsは、気候科学者の分析として、冬季オリンピックの開催は今後ますます困難になると報じている。*1
冬季オリンピックは、安定した寒冷条件と自然降雪を前提に設計されてきた。しかしその前提は、すでに多くの開催地で成立しなくなっている。平均気温の上昇によって氷点下の日数が減少し、降雪は不安定化し、競技日程全体を自然条件に委ねることが難しくなっている。世界自然保護基金(WWF)の気候変動担当上級副会長であるマーシーン・ミッチェルは、「雪を得るために必要な氷点下の日数は、すでに約20%減少している」と指摘する。この減少は、将来予測ではなく、現在進行形の現象である。
「雪はあるが、足りない」という現実
2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックでは、イタリア・ドロミテ山脈一帯で、約5万立方メートル(176万立方フィート)の人工雪が製造される。大会運営側はBBCに対し、今大会で使用される雪の約85%が人工雪であると説明している。理由として挙げられているのは、「大会期間を通じて、均一で公平かつ安全な競技条件を保証するため」である。*2
イタリア北部ドロミテ山脈に位置する山岳リゾート都市で、首都ローマから北へ直線距離で約520km離れているコルティナ・ダンペッツォは標高1,816メートルに位置し、過去には冬季競技に十分な自然降雪が見込める地域とされてきた。それでもなお、自然雪のみでは競技環境を維持できないという判断が下されている。
この傾向は例外ではない。2022年北京冬季オリンピックでは、史上初めて全競技が100%人工雪に依存して実施された。The Conversationは、この事実を、「冬季オリンピックが自然条件から技術条件へと重心を移した転換点」と位置づけている。*3
雪質の変化が競技リスクを変える
人工雪は、自然雪と同じ「雪」という名称を持つが、その構造は大きく異なる。英国ラフバラー大学が2022年に公表した研究によれば、
ここから先は「ThinkESG プレミアム」会員限定の
コンテンツです。
4つの特典が受けられる「ThinkESG プレミアム会員(1ヶ月定期購読)」の詳細についてはこちらをご覧ください。
「ThinkESG プレミアム会員(1ヶ月定期購読)」へはこちらからお申し込みいただけます。